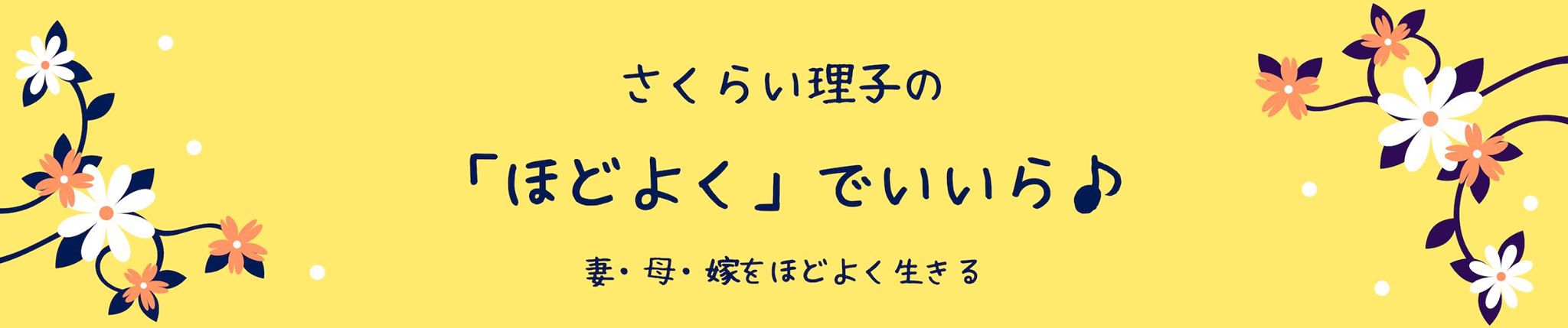お子さんの「しもやけ」にお悩みですか?
「しもやけ」になると赤くなって腫れたり、じんじん痛がゆくなったり、ひどくなると水ぶくれになってしまって大変ですよね。
幼い子どもでは痛みやかゆみが我慢できず、泣き出してしまうこともあります。
この記事では、そんなとっても辛い「しもやけ」にならないための予防法をご紹介します。
我が家の次男もっちゃんはこの時期になると毎年「しもやけ」に悩まされていたのですが、今回ご紹介する予防法によって、この冬は「しもやけ」になっていません。
これを読んで実践すれば、お子さんが「しもやけ」で苦しまずに済むかもしれません。
また、すでになってしまった「しもやけ」の対処法についてもご紹介しますね。
「しもやけ」はどうしてなるの?

「しもやけ」は、寒さで血のめぐりが悪くなって起こる炎症です。
とくに手足の指先がなりやすいのですが、肌が露出している頬っぺたや鼻先、耳たぶなども「しもやけ」になります。
冬場の気温が5℃前後で、一日の気温差が10℃以上になると「しもやけ」になりやすいと言われています。
「しもやけ」はとにかく予防が大切!

もっちゃんの「しもやけ」が特にひどくなってしまった昨年と一昨年は、近所の皮膚科にかかりました。
そこで先生から言われたのは、「『しもやけ』は一度なってしまうとすぐには治らず、症状が続くと本人もかなり辛いので、しっかりと予防をしてあげましょう」ということでした。
確かにもっちゃんの「しもやけ」の治りは遅く、昨年は完治するまで1ヶ月以上もかかってしまいました(涙)。
そこでこの冬は「しもやけ」にならないよう、次でご紹介する皮膚科で教えてもらった予防法に取り組んでいます。
「しもやけ」にならない!3つの予防法
1.冷やさないよう保温する

外出するときは手ぶくろや厚手の靴下、帽子などで防寒します。
また家の中でも足が冷えてしまわないように、靴下をはかせるようにします。(もっちゃんは家に上がるとすぐ靴下を脱ぐクセがあるので大変です)
そしてその時に注意したいのは、汗をかいたらしっかり拭いて乾かしてから新しい手ぶくろや靴下にかえさせることです。
手ぶくろや靴下が汗で濡れたままだと、水分が蒸発するときに皮膚表面の温度を下げてしまい、「しもやけ」ができやすくなるからです。
2.血行を良くする

これは「しもやけ」になってしまった場合にも有効な方法で、患部をを温水と冷水に交互につけることで血行を良くします。
もっちゃんの場合はお風呂に入った時に洗面器に水を入れておいて、手足を温めたり冷やしたりしています。
また湯船の中で指先のマッサージもしています。

患部だけでなく、からだ全体の血のめぐりを良くするためには全身運動が効果的です。
もっちゃんは以前は学校の体育以外に運動はしていませんでしたが、昨年春からスポーツ少年団でミニバスケットを始めました。
以前はお風呂に入ってもすぐに冷たくなってしまっていた手先や足先が今年はポカポカしているので、定期的な運動の効果なのかな?と思っています。
特別な運動を始めなくても、小学校の休み時間の外遊びを増やしたり、休日に公園や室内遊具などで体を動かすのも良さそうです。
3.ビタミンEを多く含む食べものをとる

血行を良くする効果のあるビタミンEを多く含む食べものを日々の食事に取り入れます。
【ビタミンEを多く含む食べもの】
※皮膚科でもらったプリントより抜粋
-
- ナッツ類:アーモンド、ピーナッツ
- 野菜:モロヘイヤ、赤ピーマン、かぼちゃ
- 魚卵:イクラ、タラコ
- 魚類:うなぎ、はまち
- 大豆製品:納豆、きなこ
なかでもナッツ類は、おやつとして手軽に食べられるので特におすすめです。
さらにこれらをビタミンCと一緒にとるとビタミンEの吸収率を高めてくれるそうなので、我が家では静岡名産のみかんをよく食べています。
もっちゃんは魚卵やうなぎ、納豆がずっと苦手だったのですが、
「これを食べると『しもやけ』になりにくくなるんだって。」
とプリントを見せながら教えると、それまで食わず嫌いだった納豆については食べられるようになってビックリしました。
それでも「しもやけ」になったらこの対策
「しもやけ」になってしまっても大丈夫、以下の対策で乗り切りましょう!
これも皮膚科で指導された方法です。
※赤黒く変色したり出血や水ぶくれなどのひどい症状がみられる場合には皮膚科を受診しましょう
1.靴下を重ね履きしてカイロを貼る
靴下を普通に履いたら、「足用のカイロ」を足の裏(つま先部分)に貼り、さらにその上からもう一枚靴下を履かせます。
もっちゃんの話では、小学校の授業中にじっと座っていると足先の冷え込みがひどかったそうですが、カイロを貼ってからはつま先が温かくてすごくいい♪と言っていました。
2.温水と冷水につけて血行を良くする
これは先ほど予防のところでもご紹介した血行を良くする方法です。
温めるとかゆくなって辛いかもしれませんが、早く治すためにもできる範囲で取り組めるといいですね。
3.ビタミンE入りのクリームを塗る
皮膚科ではビタミンE入りのクリーム(名称:ユベラ)が処方されました。もっちゃんはこれを1日3回くらい患部に塗りこんでいました。塗る時についでに優しくマッサージしてあげるのもいいですね。
症状がひどい場合は、皮膚科でビタミンEの飲み薬が処方される場合もあるようです。
塗り薬も飲み薬も、冷えや血行を良くして「しもやけ」の症状を軽くしてくれる効果が期待できます。
市販では、画像にあるようなビタミンE入りのクリームが入手できます。(興味のある方は画像をクリックしてみてくださいね)
どうして兄弟姉妹でちがう?
「しもやけ」になる・ならない

余談ですが、これは私がどうしても気になって調べてみたのでご紹介します。
私は小学生の時に毎年両手の指が「しもやけ」になって辛い思いをしてきました。登校する時に手袋をしていても指がかじかんでしまい、学校に着いてランドセルの中のものを取り出すのに一苦労でした。
ところが姉のほうは、手袋もしていないのに一度も「しもやけ」になったことがありません。
ホントうらやましかったな~。
そしてうちの息子たち2人についても同じように兄弟で異なります。
兄のほーくんは「しもやけ」になったことは一度もありませんが、弟のもっちゃんは保育園に通い始めた頃から毎年、手足の指が「しもやけ」になっていました。
どうして同じような生活を送っているのに、「しもやけ」になる人とならない人がいるのでしょうか?
それはどうやら、遺伝や体質が関係するようです。
しもやけの原因は、もちろん冷たい空気に曝されることですが、同じように寒気に当たっても、しもやけを起こしやすい人と起こしにくい人がいることが知られています。つまり、冷気に曝された後の血流の障害の程度とそこからの回復には遺伝的な差があって、しもやけになりやすい体質の人と、なりにくい体質の人がいると考えられています。
(引用元:日本臨床皮膚科医会「ひふの病気」)
そういうことだったんですね~。
体質の違いなら仕方ありませんが、なりやすい体質であっても予防をしっかりすることで、できる限り「しもやけ」にはなりたくないものです。
まとめ

今回は、とっても辛い「しもやけ」からお子さんを守る方法と「しもやけ」になった場合の対策をご紹介しました。
【予防法】
- 冷やさないよう保温する
- 血行を良くする(温水冷水・運動)
- ビタミンEを多く含む食べものをとる
【対策法】
- 靴下を重ね履きしてカイロを貼る
- 温水と冷水につけて血行を良くする
- ビタミンE入りのクリームを塗る
これでお子さんの「しもやけ」予防と対策はバッチリですね!
まだまだ続く寒い冬を、元気に楽しく過ごしていきましょ~(^^♪
★もっちゃんオススメの足用カイロはこちら ↓ ↓