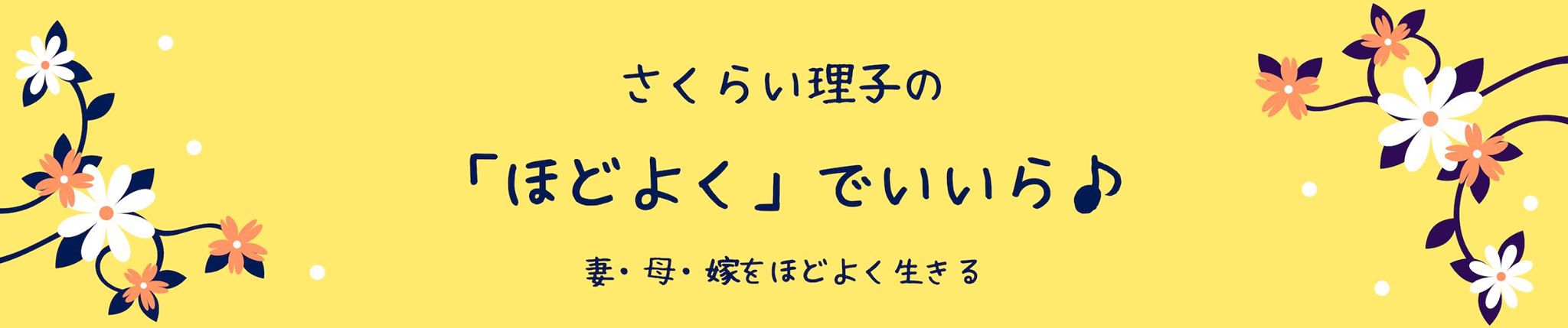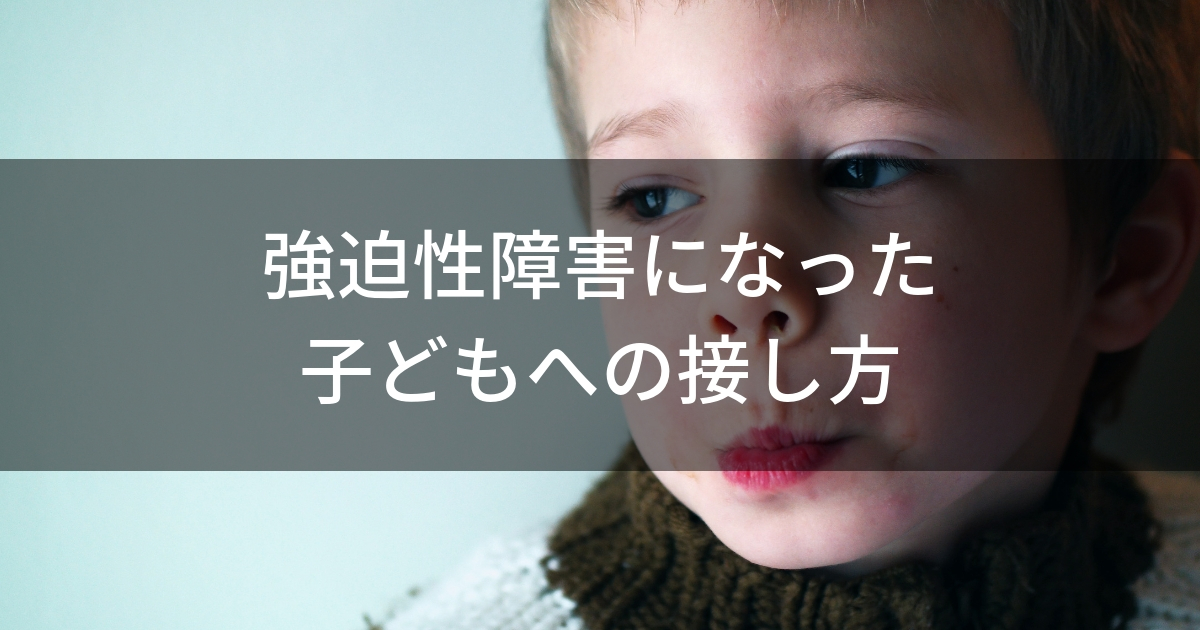
我が家の次男もっちゃんは、現在小学2年生です。
今は元気に暮らしていますが、昨年の年末からお正月にかけて、もっちゃんは別人のように変わってしまっていたのです。
突然現れたもっちゃんの強迫性障害の症状と、それが治まるまでの数ヶ月の出来事について、私の体験を少しずつ書いていきたいと思います。
子どもが強迫性障害になった場合、家族はどのように接したら良いのでしょうか?また、気をつけるべきことはあるのでしょうか?
この記事では、強迫性障害の症状が出ている子どもへの家族の接し方について私の体験をもとに書きました。症状を悪化させないためには家族の接し方がとても大切なので、ぜひ知っておいていただけたらと思います。
※この記事は連載ものです
- 強迫性障害になった子どもへの家族の接し方と対応(体験談1)←いまここ
- 子どもが強迫性障害になった時の病院や相談窓口は?(体験談2)
- 子どもの強迫性障害「収集癖」の具体的な10の症状(体験談3)
- 強迫性障害の「巻き込み」に応じないための5つのコツ(体験談4)
- 子どもの強迫性障害、病院へ行かず薬なしで克服した方法(体験談5)
- 強迫性障害の子ども、小学校へは行かせる?休ませる?(体験談6)
- 強迫性障害の原因が判明!岡嶋美代先生のカウンセリング(体験談7)
- 強迫性障害を克服した本人へのインタビューと家族の変化(体験談8)
楽しみにしていた冬休み

12月下旬、子どもたちが小学校の冬休みに入った初日、私はインフルエンザにかかって高熱を出していました。そのせいで、家族みんなで楽しみにしていたクリスマスケーキ作りもクリスマス会も、できなくなってしまいました。子どもたちはガッカリです。
夫や子どもたちにインフルエンザをうつさないようにと、私は自宅2階の部屋に閉じこもり、退屈な時間を過ごしました。子どもたちは心配そうに時々様子を見に来てくれましたが、うつるからと部屋には入れないようにしていました。
数日後、やっと起きられるようになった私は、子どもたちを連れて買い物に出かけました。
突然のパニックと号泣
その日は強い風が吹いていました。駐車場で私が車のドアを開けた時、車の中にあった空のビニール袋がふわっと舞い、外に飛んでいきました。それを見たもっちゃんが、
「あーーーっ!ビニール袋が!飛んでっちゃった!!早く!早く追いかけないと!!」
と大騒ぎし始めました。
「もっちゃん、あれはもう取れないよ。追いかけても無理だよ。」
と私が言っても聞こえていないようです。ものすごい形相でビニール袋を走って追いかけていきます。
ところがビニール袋は家の屋根くらいの高さまで舞い上がり、垣根の向こうに見えなくなってしまいました。
するともっちゃんはパニック状態で泣き始めたのです。
帰りの車の中でも、家についてからもそれはおさまらず、どうしようどうしようどうしようと泣きながら部屋の中をウロウロしています。
長男のほーくん(当時小4)は、あまりにもっちゃんの様子がおかしいので、私と顔を見合わせて首をかしげていました。
しばらくたってもまだ、もっちゃんのパニックはおさまりません。
するとほーくんが何か思いついたようにもっちゃんのところへ行き、コソコソと耳打ちをしたのでした。するともっちゃんは、
「え?そうだったの?なーんだ、よかったー(ニコニコ)。」
急にいつものもっちゃんに戻ったのです。
不思議がる私に、ほーくんはもっちゃんに聞こえないようにこう言いました。
「あのビニール袋ね、実はオレがちゃんと拾ってきてたんだよってとりあえず言っといた。」
その手には、飛んで行ったものと同じタイプのビニール袋が握られていました。どうやら家にあったもので代用したようです。とにかくもっちゃんが落ち着いたということで、私はひとまずホッとしました。
家に帰った夫にこのことを話すと、なんと夫も思い当たることがあると言うのです!
それは、私がインフルエンザで寝込んでいる間に起きたことでした。夫が子ども2人を連れて遊びに行った公園で、折れた木の枝をどうしても持って行きたいともっちゃんが泣いたのだそうです。
枝の長さは1.5メートルくらいで太さも結構あったので、夫は持って帰るのは無理だと言ったそうなんですが、どうしてもと聞かなかったそうです。そこで仕方なく、木の枝を持ち帰り、裏の畑に置いたところでやっと落ち着いたというのです。
症状の進行と家族の困惑

次の日から今度は、
「○○ってもしかして、もう捨てちゃった?」
という質問を私や家族に頻繁にしてくるようになりました。
捨てたかと聞かれる物はほとんどが不要品で、もうとっくの昔に捨てた物だったり、最近捨てた物などがほとんどでした。(割れてしまった茶碗など)しかも捨てた時には本人が平気で捨てているのです。
なので、「捨てたよ。」と答えると「どうして捨てちゃったの?」とパニック状態で泣き叫ぶのでした。さらにはごみ収集場やごみ処理場まで取りに行く!と泣くのです。
その頻度はどんどん増していき、また泣き声は隣の家にも聞こえるんじゃないかというくらいの大声でした。
そういうことを何度も繰り返すうちに、もっちゃんからはいつもの笑顔が見られなくなっていきました。常に何かの恐怖に支配されているようでした。
私たち家族は、もっちゃんがどうしてこんなことを言い出すのか訳がわかりません。ただただ、号泣するもっちゃんを抱きしめることしかできませんでした。
「強迫性障害」の「収集癖」?
もっちゃんは普段から聞き分けが良く、駄々をこねるようなこともない子でした。それなのにパニックになるほど何かにこだわる様子と、気になっていることが納得できれば我に返る様子から、これは通常の精神状態ではないなと思い、私はインターネットでいろいろ調べてみました。
するともっちゃんの様子は、「強迫性障害」の症状なのではないかという答えにたどり着いたのです。
強迫性障害(Obsessive Compulsive Disorder=OCD)とは、自分でもコントロールできない不快な考え(強迫観念)が浮かび、それを振り払おうとして様々な行為(強迫行為・儀式)を繰り返し行い、日常生活に支障をきたす、あるいはまったく日常生活が立ち行かなくなってしまう不安障害(※)です。
※不安障害…パニック障害、社会性不安障害など、「不安」を主症状とする精神疾患全般を意味する。
≪参考文献≫2017年 株式会社ナツメ社 原井宏明・岡嶋美代著『やさしくわかる強迫性障害』
「強迫性障害」には様々な症状があるのですが、もっちゃんはその中でも物に異常に執着してしまう「収集癖」に当てはまるのではないかと考えました。この「収集癖」はとにかく物が捨てられなくなるので、ひどくなると最終的には家がごみ屋敷のようになってしまうといいます。

私は、大人になったもっちゃんがごみ屋敷でごみに埋もれている様子を想像してしまい絶望的な気持ちになりました。
が、落ち込んでいる暇はありません。今はとにかく、この状況をなんとかしなくては!
家族の接し方で一番大切なこと
さらに強迫性障害について調べてみると、家族が気をつけることとして『本人の強迫に巻き込まれない』ということがわかりました。家族が本人の強迫に付き合って巻き込まれていると、症状がどんどん悪化してしまうというのです。
もっちゃんの場合で言えば、巻き込まれるというのは、例えば捨てたものを捨ててないよとごまかしたり、ごみ箱の中をあさって捨てた物を探し出すのを手伝うようなことです。
逆に、本人の強迫に巻き込まれない接し方は次のようになります。
- 捨てたものについて聞かれたら、「知らない。」と言うか、「捨てたよ。」と本当のことを言う
- 捨てたものを拾いに行きたいと言っても「それは無理だよ。」と答え協力しない
ですが、これは本人も周りもものすごく苦しい思いをします。
聞かれたことに対して、本人が納得するように適当にごまかしていればもっちゃんは笑顔でいられるのに、それはできないのです。本人が怒って泣き叫んでパニックになると分かっている対応を選択しなければならないんです。
もっちゃんの苦しむ顔を見るとやりきれませんでしたが、私は何度も自分に言い聞かせました。とにかく今、もっちゃんの症状を悪くしないためにはこれしかないんだと。夫やほーくんにもそうするしかないんだということを必死で説明して、なんとか同じように対応してもらいました。
いつもはのんびり楽しく過ごしている冬休みでしたが、その時の家の中はどんよりと重苦しい空気で満ちていました。そして一日がものすごく長く感じました。

しかし、本人も周りも苦しむ中で1つだけわかったことがありました。
それは、パニックはそう長くは続かないということです。一時的にはこちらがうんざりするほど大騒ぎするのですが、毎回長くても15分程度で落ち着くのです。
いつまた捨てた物について聞かれるのかドキドキしながらも、パニックは15分程度我慢すれば通り過ぎる。その時の私たちにとっては、そのことだけが救いでした。
その日はすでに夜になっていたので、とにかくこれは病気なんだから、明日病院へ行って診てもらおう。そうすればすべてが解決する、と思いながらその日は寝床につきました。
まとめ
強迫性障害になった家族への接し方で大切なこと、気をつけることはまずはとにかくこれです。
- 本人の強迫観念からくる強迫行為(儀式)に巻き込まれない
もっちゃんの場合も完璧にできていたわけではありませんが、家族全員が極力巻き込まれないよう気をつけて過ごしました。そしてそれにより、症状の悪化を最小限に抑えることができたのです。
次回は病院を探すところから書きたいと思います。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
★ご感想やご質問など、お気軽にコメントいただけると嬉しいです
★おすすめの本はこちらの記事で詳しくご紹介しています
↓ ↓