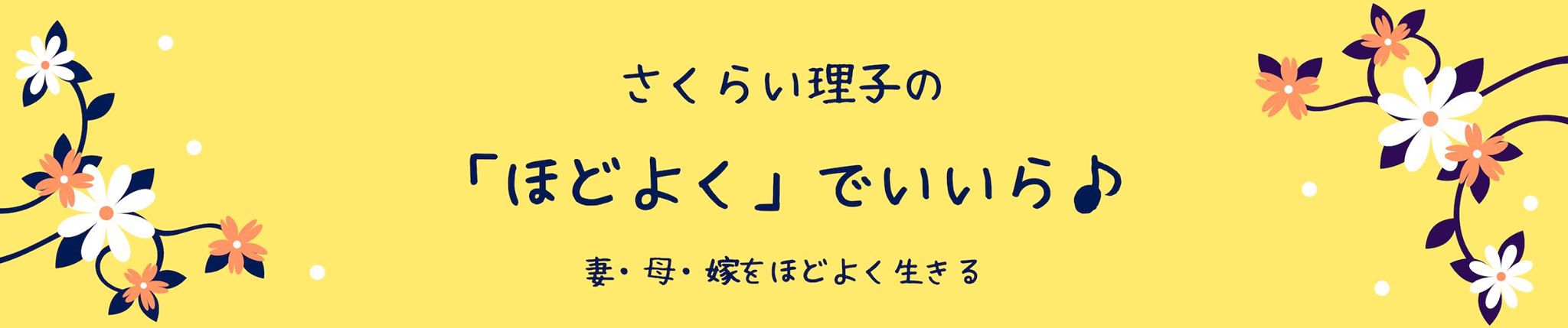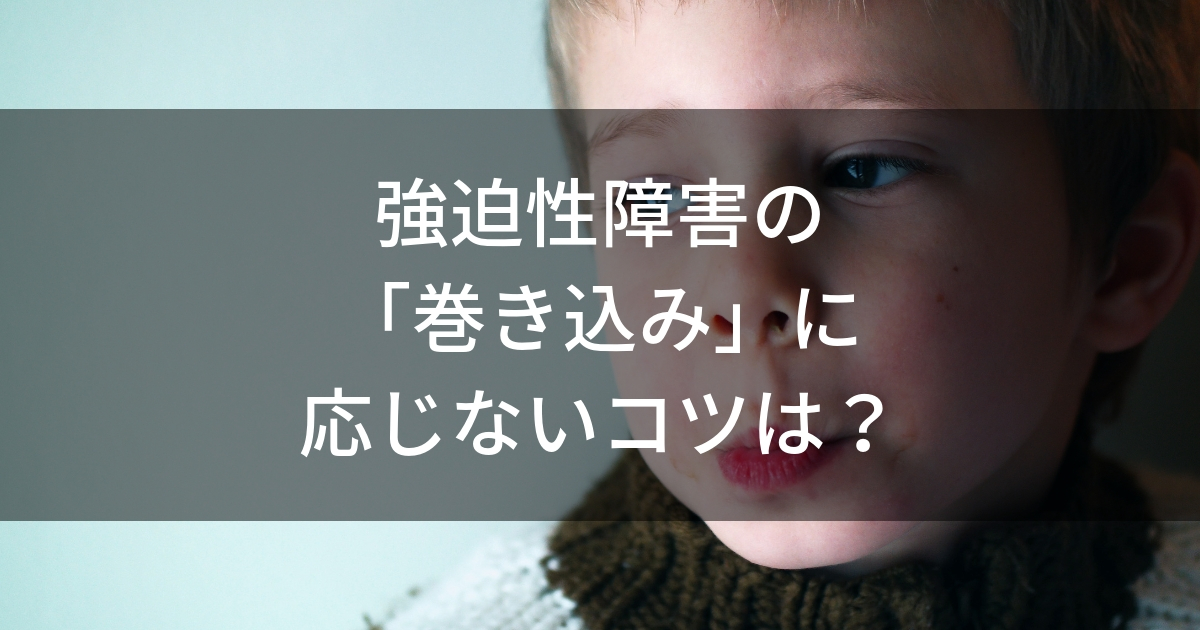
強迫性障害は、家族にも自分と同じような行動をとるように強要したり確認の代行をさせるなど、家族を巻き込みやすい病気です。
求めに応じないと泣きわめいたりパニック状態になったりするので、かわいそうで家族はつい巻き込まれてしまいがちです。
ところが、言うとおりにしていると要求はさらにエスカレートしていき、強迫性障害の症状は悪化してしまいます。
では、家族が巻き込まれないためにできることはあるのでしょうか?
この記事では、我が家の次男もっちゃん(当時小学1年生)が強迫性障害になった時の体験をもとに、家族が巻き込まれないためのコツをまとめました。
これを読めば、もう巻き込みに応じなくてすむことでしょう。
※この記事は連載ものです
- 強迫性障害になった子どもへの家族の接し方と対応(体験談1)
- 子どもが強迫性障害になった時の病院や相談窓口は?(体験談2)
- 子どもの強迫性障害「収集癖」の具体的な10の症状(体験談3)
- 強迫性障害の「巻き込み」に応じないための5つのコツ(体験談4)←いまここ
- 子どもの強迫性障害、病院へ行かず薬なしで克服した方法(体験談5)
- 強迫性障害の子ども、小学校へは行かせる?休ませる?(体験談6)
- 強迫性障害の原因が判明!岡嶋美代先生のカウンセリング(体験談7)
- 強迫性障害を克服した本人へのインタビューと家族の変化(体験談8)
強迫性障害の知識を深めよう
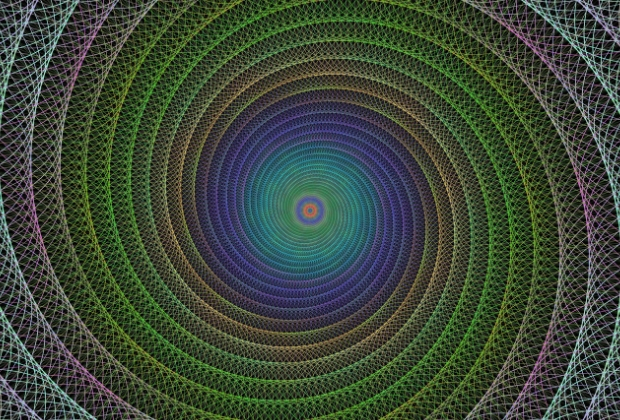
巻き込みがどのように症状を悪化させてしまうのかを知ることで、強迫性障害によるパニック状態を目の前にしても冷静な行動をとることができるようになります。
まずは、なぜ巻き込みが良くないのかを確認してみましょう。症状を悪化させる仕組みは以下のとおりです。
本人が強迫観念に基づく行為(強迫行為・儀式)を家族に要求し、家族がそれに応じる
↓
本人の不安は一時的に軽減して落ち着くが、その後強迫観念が強くなる
↓
要求がエスカレートし、家族がそれに応じる
↓
一時的には落ち着くが、その後強迫観念がさらに強くなる
このように強迫観念がどんどんエスカレートしていくと、強迫行為(儀式)のために家族の生活が立ち行かなくなってしまいます。
そのうえ、本人に「このままではまずい、この状況を変えたい」という気持ちが生まれにくくなってしまい、治療から遠ざかってしまいます。
このような負のスパイラルから一刻も早く抜けだすためにも、辛いことではありますが家族は巻き込みに応じてはいけないのです。
長期的な視点で考えよう

目の前でパニックを起こして泣き叫ぶ我が子を見れば、親としてはどうにかして落ち着かせたり、楽にしてあげたいと思うでしょう。本人の要求に応じたり子どもの質問に気休め的に答えたりして落ち着かせることは、その場限りのことであれば良いでしょう。
でも、長期的にみたらどうでしょうか?
家族が巻き込まれれば症状はさらに悪化していき、要求はどんどんエスカレートしていくのです。
パニック状態はもっちゃんの場合、長くても15分程度で治まりました。落ち着くまでは泣いて暴れたりするので大変でしたが、強迫観念はいつまでも続きません。なので私たち家族は「15分の辛抱だから」を合言葉にして耐えていました。
巻き込まれないという対応はその場では辛いことでしかありませんが、明るい未来を信じていきましょう。
「病気」と「本人」は切り離して考えよう

もっちゃんがまさにそうだったのですが、強迫性障害の症状が出ている時は急に別人になってしまったようにみえることがあります。
今まで見たことのない鋭い眼つきで睨まれたり、「お母さんのバカ!もう大嫌い!」などと凄んだ声で何度も言われると、精神的に辛くなってしまうこともありました。
でもある時気づいたんです。それは病気が言わせている言葉であり、病気がさせている態度なんだと。だから性格まで変わってしまったのでは?と心配することはありません。
現に元気になったもっちゃんは今、以前と変わらない明るくてひょうきんなもっちゃんに戻りました。
ですから、例えひどいことを言われても不安にならないで、気持ちに余裕をもって対応していただけたらな、と思います。
家族全員で取り組もう

お母さんは断固として要求に応じないけれど、子どもに泣かれることに弱いお父さんは要求に応じてしまう、というのでは困ります。また、おじいちゃんやおばあちゃんが孫可愛さに要求に応じてしまう、というパターンもありがちです。
このような場合、お父さんやおじいちゃん、おばあちゃんに「巻き込まれることがなぜいけないのか」「巻き込まれていると将来どうなってしまうのか」をきちんと理解してもらうと協力を得られやすいでしょう。
家族が一丸となって対応を統一することで、症状の進行や悪化を防ぐ効果が高まります。それが本人のためであり、家族のためでもあるのです。
我が家の場合は、もっちゃんの兄であるほーくん(当時小4)がつい要求をのんでしまうことがあったので、その度に「それはもっちゃんのためにならないんだよ」と理由をこんこんと説明しました。はじめは説明している意味がわからないほーくんでしたが、少しずつ理解してくれ、協力してくれるようになりました。
上手に息抜きをしよう

育児を中心的に担っているお母さんが陥りがちなのが、問題を一人で抱え込んでしまって自分のほうが参ってしまうことです。
強迫性障害に巻き込まれないようにすることは、体力的にも精神的にも想像以上に大変です。
もっちゃんは当時小学1年生でしたが、パニック状態で暴れた時に出す力は相当強く、私でも負けそうになる時がありました。また、ことあるごとに本人と真剣に向き合わなくてはならないので、精神的な消耗も激しかったです。
ですから、たまには外に出かけたり好きなことをして息抜きすることをおすすめします。他の人にお願いして、リフレッシュできるような時間をぜひ持ってもらえたらな、と思います。

お母さんが苦しんでいることを子どもはちゃんと見ています。
私はある日、
「お母さん、ボクがこんな風になっちゃってごめんね。」
ともっちゃんに言われてしまいました。きっといっぱいいっぱいなのが伝わってしまったのでしょう。
それからは、もっちゃんを夫にお願いして出かける時間をとるようにしました。
近所の喫茶店に行って好きなコーヒーを飲んだとき、肩の力が抜けてホッとしたのを覚えています。そして、「もっちゃんに心配かけないように、私が元気でいなくちゃなぁ。」としみじみ思ったのでした。
強迫性障害は、今日明日ですぐに良くなるというものではありませんから、一人で無理を重ねていたのでは身が持ちません。どうか自分のことも労わって、大切にしてあげてくださいね。
まとめ

今回は、家族が強迫性障害の巻き込みに応じないためのコツを5つご紹介しました。
- 強迫性障害の知識を深めよう
- 長期的な視点で考えよう
- 「病気」と「本人」は切り離して考えよう
- 家族全員で取り組もう
- 上手に息抜きをしよう
強迫性障害の家族を持つと、つい要求に応じてしまいたくなりますが、そんな時はこの記事を思い出していただけたらと思います。
少しでもお役に立てれば幸いです。
≪参考文献≫2017年 株式会社ナツメ社 原井宏明・岡嶋美代著『やさしくわかる強迫性障害』
※参考文献はこちらの記事で詳しくご紹介しています
↓ ↓
強迫性障害にはこの本がおすすめ!『図解やさしくわかる強迫性障害』
★ご感想やご質問など、お気軽にコメントいただけると嬉しいです