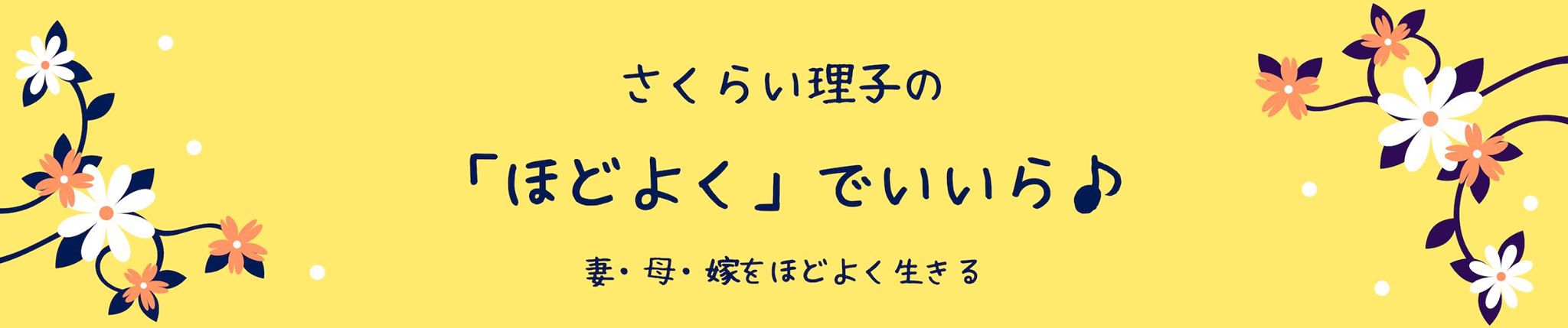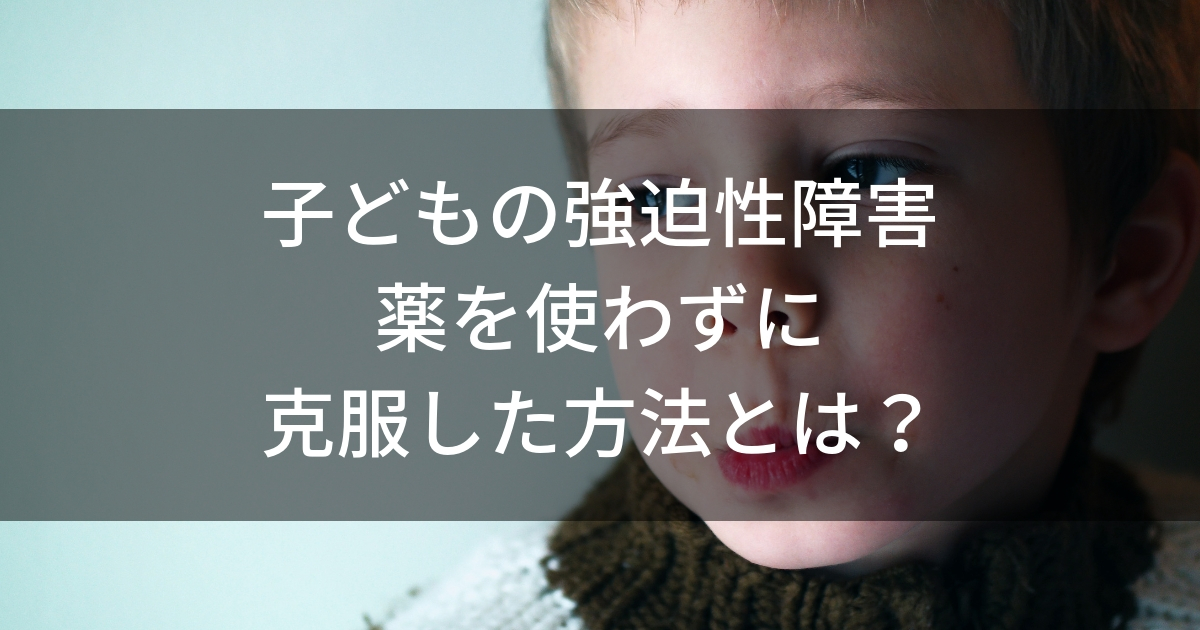
子どもが強迫性障害になった時にまず私が考えたことは、「病気なんだから、とにかく病院へ行って薬を処方してもらおう」ということでした。強迫観念を薬で抑えることができれば、それで治ると思っていたのです。
ところが強迫性障害について調べるうちに、薬の子どもへの副作用の影響がはっきりしていないことや、根本的な治療法として「ある行動療法」が有効であることがわかりました。
この記事では、我が家の次男もっちゃん(当時小学1年生)が、どのようにして薬物療法以外で強迫性障害を克服したのかを書いていきます。
強迫性障害のお子さんを持つ方に、何か少しでも参考になればと思います。
※この記事は連載ものです
- 強迫性障害になった子どもへの家族の接し方と対応(体験談1)
- 子どもが強迫性障害になった時の病院や相談窓口は?(体験談2)
- 子どもの強迫性障害「収集癖」の具体的な10の症状(体験談3)
- 強迫性障害の「巻き込み」に応じないための5つのコツ(体験談4)
- 子どもの強迫性障害、病院へ行かず薬なしで克服した方法(体験談5)←いまここ
- 強迫性障害の子ども、小学校へは行かせる?休ませる?(体験談6)
- 強迫性障害の原因が判明!岡嶋美代先生のカウンセリング(体験談7)
- 強迫性障害を克服した本人へのインタビューと家族の変化(体験談8)
専門家のアドバイスを受ける

大晦日も迫った12月29日、もっちゃんの症状が出てからちょうど1週間が経とうとしていました。
家族が本人の強迫行為に巻き込まれないようにしたことで、もっちゃんの症状は悪化こそしないものの、「体験談3」で書いたとおり日常生活にはかなり支障をきたしていました。
そこで我が家では、強迫性障害について書かれた書籍『図解 やさしくわかる強迫性障害』を参考に、家庭での治療を試みることにしました。
ただ、本の中にも「『親が治療者になる』といってもプロではないので、専門家(行動療法の相談ができる精神科医など)に相談してアドバイスを受けるとよい」とありましたので、まずは相談先をさがすことにしました。
家の近くで行動療法を行っている病院はないため、インターネットで相談できるところがないか検索してみました。すると、あるウェブサイトが目にとまりました。

それは、強迫性障害の認知行動療法を専門にされている臨床心理士の先生のサイトで、嬉しいことに自宅にいながら電話やスカイプでカウンセリングを行っているとあります。
その先生のブログを読んでみると、もっちゃんのような小学生の強迫性障害への対処法もわかりやすく書かれているし、なにより文章を読んでいるだけで前向きな気持ちになれました。
早速問い合わせてみると、年末年始のお休みとすでに入っている予約があるため、年が明けた8日なら予約がとれるとのことでした。そこで、60分間の電話による家族カウンセリング(単発)を予約しました。
カウンセリングの翌日9日には冬休みが明けて小学校が始まるため、前日に予約できたことはラッキーだと思いました。まずは小学校へ行くことを目標に、できることから取り組んでいくことにしました。
強迫性障害に有効な行動療法:エクスポージャーと儀式妨害
強迫性障害には、「ERP(Exposure & Ritual Prevention):エクスポージャーと儀式妨害」という行動療法が有効だといわれています。これは、不安や恐怖にあえてさらすことで、症状を好転させる治療法のことです。
「収集癖」タイプのもっちゃんの場合で例をあげると、十分に惜しみながら、できる物から毎日少しずつ溜めた物を捨てていきます。恐れる状況とあえて向き合い行動することで、惜しいという感覚が徐々に弱まっていきます。
「不安や恐怖にあえてさらす」と聞くと苦しいことばかりを想像してしまいますが、実は幼い子どもであればゲームのように取り組むことができるのです。
書籍『図解 やさしくわかる強迫性障害』にはそれぞれのタイプに応じたERPのやり方が詳しくわかりやすく書かれていますので、もしもご家庭でERPに取り組まれるのであればぜひ読まれることをおすすめします。
実際に行ったERPと言葉かけ
家庭でのERP成功の鍵を握るのは、親からの言葉かけです。ここでは、本やカウンセラーの先生のブログを参考に私がやってみた中で、もっちゃんに特に効果があったERPと言葉かけを2つご紹介します。
強迫に名前をつけて、「言い返し」をするよう教える

強迫観念に『気にする君』という名前をつけて、もっちゃん自身とは切り離して考えるように教えました。そうすることで、自分が悪いんじゃなくて自分の中の『気にする君』が悪いんだ、と強迫観念を客観的にとらえることができるようになりました。
そして、「『気にする君』なんてやっつけてやる!」「『気にする君』、お前なんかには絶対に負けないぞ!」というような「言い返し」を教えることで、ERPへのやる気を引き出しました。
具体的には、「よーし、『気にする君』をやっつけるためには、使ったティッシュペーパーを1枚だけごみ箱に捨ててみよう!」といった具合です。
ちなみに、この『気にする君』という名前はもっちゃんと一緒に考えて決めました。それから、絵の得意な兄のほーくん(当時小4)に『気にする君』をイメージしたキャタクターを書いてもらって撃退表を作りました。もっちゃんが1つごみを捨てられたら、撃退表に1枚シールを貼れます。
シールが増えていくと『気にする君』はどんどん弱っていくんだよ、と私が言うと「じゃあ、がんばる!」と言って立ち上がるもっちゃん。お父さんやほーくんも、「いいぞ、がんばれもっちゃん!」と応援します。
この方法により、家族みんなでゲームのように楽しくERPに取り組むことができました。暗かった家の雰囲気もこの方法を始めてからは明るく変わりました。
「強迫観念は強迫行為をしなくてもいつか消えるもの」と認識させる

もっちゃんの場合、強迫観念は15分くらいで薄れるのですが、子どもは大人と比べて強迫観念の苦痛が大きいらしく、嫌な考えが浮かぶと毎回パニック状態になってしまっていました。
そこで、「『気にする君(強迫観念)』は急に頭に浮かんでくるけど、時間が経てばそのうち消えてなくなるかき氷みたいなものなんだよ。」と教えました。
具体的には、「捨てたごみを収集所まで取りに行きたい!」と騒ぎ出したら、「じゃあ『気にする君』がかき氷みたいに15分で消えるかどうか、時間をはかってみよう!」と誘います。そして本当に15分位で『気にする君』が消えていくという体験を何度も繰り返すうちに、パニックを起こす回数は徐々に減っていきました。
これらの行動療法により、もっちゃんの症状は薄紙を剥ぐように良くなっていきました。強迫観念が浮かんできても強迫行動(儀式)を行わずにいられると、それが本人の自信につながるようでした。
一番嬉しかったのは、もっちゃんの笑顔を久々に見ることができた時でした。
少しずつレベルを上げていき、お正月明けにはお散歩や買い物にもチャレンジできるようになっていました。できなくて泣いてしまうこともたくさんありましたが、『気にする君』と向き合い続ける日々が続きました。
カウンセリングを受けた結果

そしていよいよカウンセリングの日が来ました。ドキドキしながら、これまでの経緯と自分たちの対応を説明し、聞きたかったことを質問してみました。
- 自分たちの対応は合っているのか?
- 今の状態で学校に行っても良いのか?
- この病気はいつ治るのか?
すると、先生は以下のように答えてくださいました。
- 今の対応で十分だが、焦りは禁物。気長に今の対応を続けていくこと。
- 小学校では他人との関わりが良いプレッシャーになるので、できるだけ行った方が良い。
- 普段どおりの生活が送れるようになるのは、現状から予想すると早くて3ヶ月後。
- 今後はこのままの対応を続けていけば大丈夫だが、この先もし親の方が自信喪失したり疲れてしまうようなことがあれば、本人も含めた対面カウンセリングも視野に入れると良い。
「今の対応で大丈夫ですよ」と言っていただけて、また他にも本人とのやりとりで判断に迷う部分について丁寧に指導していただけたことで、これからも家でERPに取り組んでいける自信がつきました。
さらに、最終手段として認知行動療法専門のクリニックが通える範囲(隣県)にあることを教えていただけたことも心強かったです。
先生の言葉がゆっくりと心に沁み込んで、話をしていると自分の体があたたかく軽くなっていくのを感じました。電話を切ると、やっぱり専門家のカウンセリングを受けて良かった!と心から思いました。
翌日9日、もっちゃんは小学校へ登校することができました。
まとめ

今回は、薬を使わずに行動療法「ERP:エクスポージャーと儀式妨害」に家庭で取り組んだ体験と、専門家のカウンセリングについて書きました。
体験者として、親子でゲームのように楽しみながら取り組める「行動療法」があることを、お子さんの強迫性障害で悩んでいる多くの方に知っていただけたらいいなと思っています。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
次回は、強迫性障害と小学校について書きたいと思います。
◆私が受けたカウンセリングのHPはこちら
↓ ↓
強迫性障害(OCD)の認知行動療法専門 KOMAYAMAカウンセリングオフィス
≪参考文献≫2017年 株式会社ナツメ社 原井宏明・岡嶋美代著『やさしくわかる強迫性障害』
※参考文献はこちらの記事で詳しくご紹介しています
↓ ↓
強迫性障害にはこの本がおすすめ!『図解やさしくわかる強迫性障害』
★ご感想やご質問など、お気軽にコメントいただけると嬉しいです